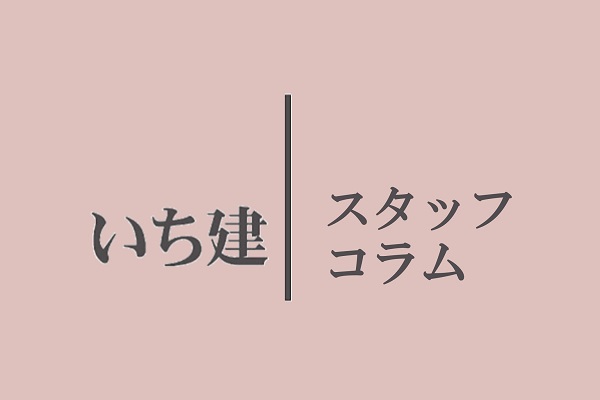親の老後、そしていつか訪れる相続。
漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に、相続税という複雑な制度は、頭を悩ませる原因の一つです。
しかし、適切な知識と対策があれば、不安を軽減し、スムーズな相続を実現できます。
今回は、相続時精算課税制度について、分かりやすく解説します。
制度の概要からメリット・デメリット、そして誰にとって最適な制度なのかを、
具体的な事例を交えながらご紹介します。
相続時精算課税制度の概要と手続きをわかりやすく解説
◆制度の目的と仕組み
相続時精算課税制度とは、生前に親から子供へ財産を贈与する際、贈与税を軽減または免除できる制度です。
2,500万円の特別控除を活用することで、贈与税を支払わずに財産を受け取ることができます。
ただし、この贈与された財産は、贈与者の死亡時に相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。
つまり、贈与税の支払いを「先送り」している状態です。
2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が新設されました。
この基礎控除額は、贈与税も相続税もかかりません。
◆選択手続きと必要な書類
この制度を利用するには、贈与を受けた人が「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限は、最初の贈与を受けた年の翌年3月15日です。
必要な書類は、届出書に加え、受贈者の戸籍謄本(または抄本)など、
受贈者と贈与者の身分関係や年齢を証明する書類です。
具体的な書類は税務署に確認しましょう。
◆2024年以降の改正点
2024年1月からの改正で、年間110万円の基礎控除が導入されました。
これにより、年間110万円までの贈与は贈与税も相続税もかからず、手続きも簡素化されました。
2,500万円の特別控除と合わせて活用することで、より効果的な相続対策が可能になります。
相続時精算課税制度のメリットデメリットと最適な人
❖メリット徹底比較
・贈与税を軽減または免除できる
2,500万円の特別控除と年間110万円の基礎控除を活用することで、贈与税の負担を大幅に減らすことができます。
・早期の財産移転が可能
必要な資金を、子供が若い時から受け取れるため、教育資金や住宅購入資金などに活用できます。
・相続税の負担軽減の可能性
相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
また、将来価値が上昇する可能性のある財産を事前に贈与することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
❖デメリット徹底比較
・暦年贈与との併用不可
一度この制度を選択すると、暦年贈与(年間110万円の贈与)に戻すことはできません。
・相続時に相続税の計算対象となる
贈与された財産は、贈与者の死亡時に相続財産に加算されます。
相続財産が多額であれば、相続税の負担が増える可能性もあります。
・小規模宅地等の特例適用不可
贈与された土地・建物は、相続税の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」の適用を受けられません。
・手続きの複雑さ
制度の利用には、届出書などの提出が必要で、手続きがやや複雑です。
❖制度が向いている人・向いていない人
この制度は、以下のような状況にある方に向いています。
・高齢で余命が短い方
相続開始前7年以内の贈与は相続税の計算対象となるため、
余命が短い場合は、この制度を活用した方が有利な場合があります。
・高額な財産を子供に贈与したい方
まとまった資金が必要な場合、この制度を活用することで、贈与税を抑えられます。
・将来価値が上昇する可能性のある財産を所有している方
不動産や株など、将来価値が上昇する可能性のある財産を、早めに贈与することで、相続税の負担を軽減できます。
一方、以下のような状況にある方には、向いていない可能性があります。
・健康で長生きできる見込みのある方
長期間にわたって少しずつ贈与していく計画がある場合は、暦年贈与の方が有利な場合があります。
・相続財産が少ない方
相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
この制度を利用するメリットは少ないでしょう。
・小規模宅地等の特例を活用したい方
贈与した土地・建物は、小規模宅地等の特例が適用されません。
まとめ
相続時精算課税制度は、生前贈与における贈与税の負担を軽減できる制度です。
2,500万円の特別控除と年間110万円の基礎控除を活用することで、税負担を効率的に管理できます。
しかし、相続時に相続税の計算対象となる点や、暦年贈与との併用ができない点、
小規模宅地等の特例が適用できない点などに注意が必要です。
ご自身の状況や将来の展望を踏まえ、この制度が最適かどうかを慎重に検討し、
必要であれば税理士などの専門家にご相談ください。
早期の財産移転や相続税対策を考える上で、重要な選択肢となる制度です。
理解を深めることで、より安心できる相続対策を立てることができるでしょう。